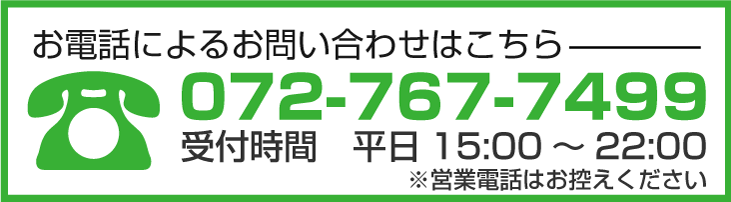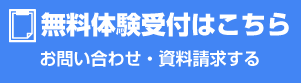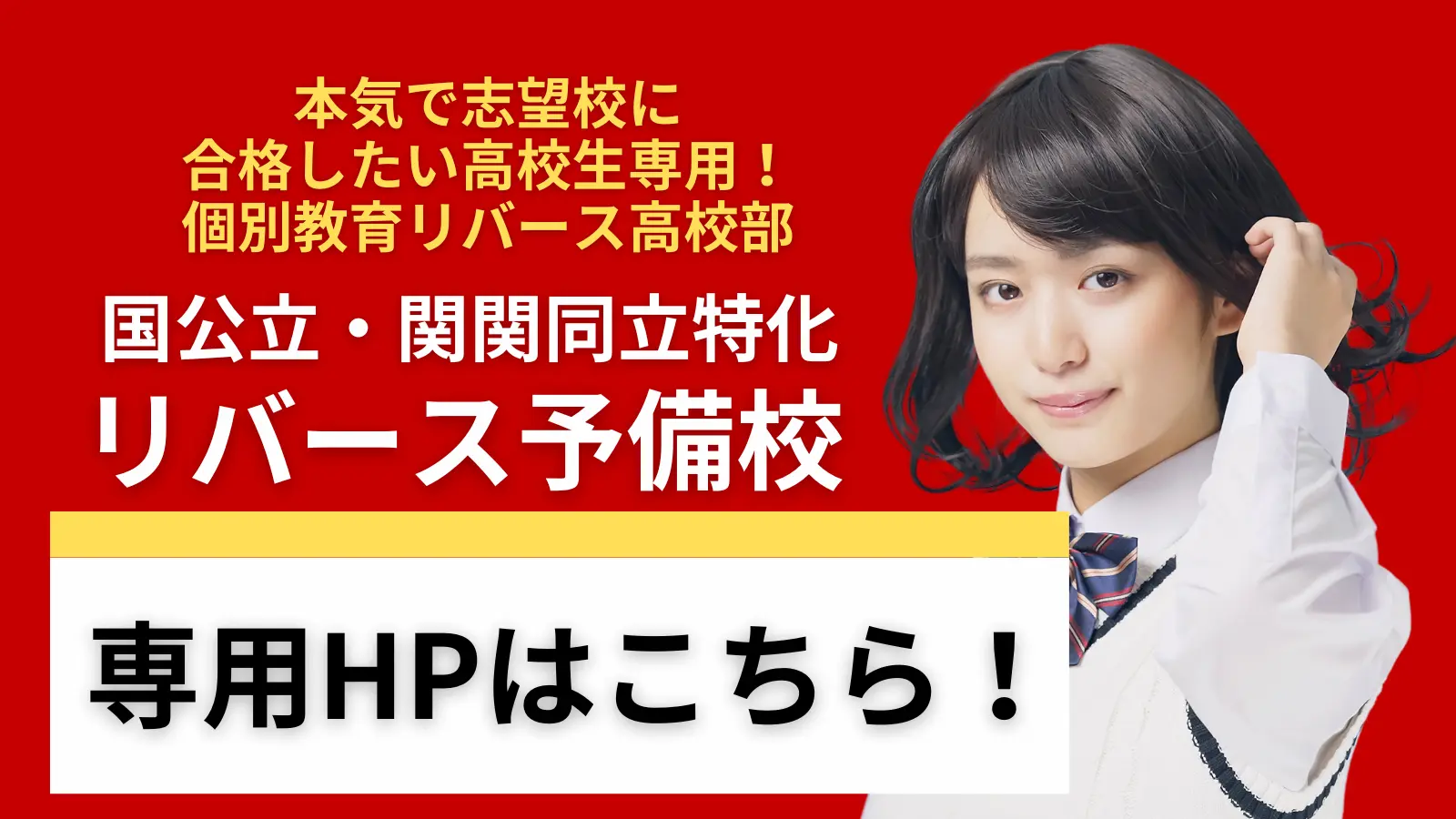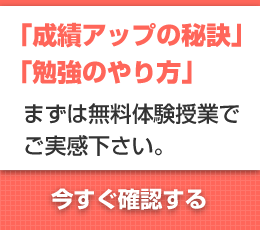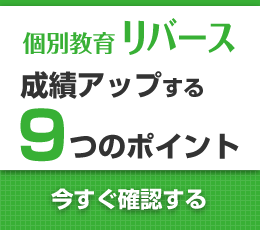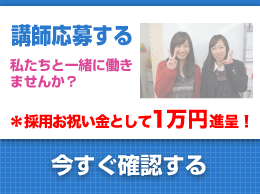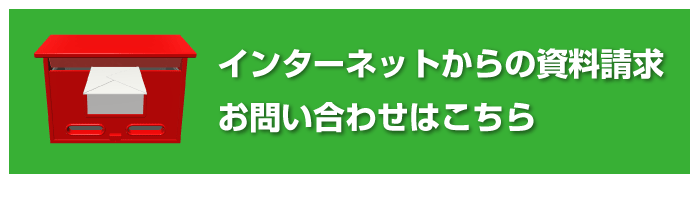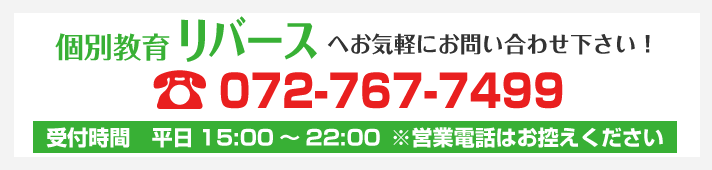こんにちは。
個別教育リバースです。
今日は、理科について取り上げます。今回で5教科すべて1つは取り上げました。
現在、二酸化炭素などの「温室効果ガス」の影響で地球の平均気温が上昇して「地球温暖化」が進行していると言われています。実際、日本の夏は年々暑くなっている印象です。
しかし、現在は地球規模の歴史で見ると、「氷河時代」の「間氷期」に相当します。北極や南極に「氷床」がある時代が「氷河時代」なのです。地球の歴史では、「スノーボールアース(雪玉地球)」に何度かなったり、また恐竜の絶滅の原因は隕石衝突による急激な気温低下と言われています。(石渡正志、滝川洋二編『発展コラム式 中学理科の教科書、改訂版、生物・地球・宇宙編』講談社ブルーバックス、2014年、P142~P145)
すなわち、「温暖化」ではなく「寒冷化」こそが生物の絶滅に深く関わっていた可能性が高いのです。
温暖化の原因は諸説あり、原因を1つに決めることは難しそうです。中学理科の教科書には、「地球温暖化が進むと、海水面が上昇して低地が水没したり、洪水や干ばつなどがふえたりするといわれている。」(『サイエンス3』啓林館、P222)として、「図21にとける北極海の氷」の写真が載っています。
あきらかにミスリードの写真です。南極大陸やグリーンランドの陸地部分の氷が溶ければ、それによって「海水面が上昇して低地が水没」するかもしれません。
しかし、北極は巨大な氷のかたまりです。グラスの飲み物に入った氷が溶けても、水があふれ出ることはありません。水が個体から液体になると、体積が減るためグラスの水があふれ出ることはありません。
「とける南極大陸の氷床」の写真なら適切ですが、上記の理由から「とける北極海の氷」の写真は不適切です。教科書以外の参考書にも、北極海の氷がとけることで「海水面が上昇して低地が水没」との記述が散見されます。
このように、小学生の理科の知識があれば教科書の間違いでも見つけることができます。
義務教育って本当に大切で役に立つと実感できる瞬間です。
ただ私は理科の専門家ではありませんので、もし間違っていれば指摘してください。