こんにちは。
個別教育リバースです。
学校休校期間中、開校時間を9:45~18:15にしていましたが、
学校再開に伴い、通常の時間帯14:00~22:00に戻させていただきます。
授業時間は、17:45~、19:10~、20:35~の時間帯です。
第2波、第3波に備えて、万全の感染対策で授業を行います。
よろしくお願いいたします。

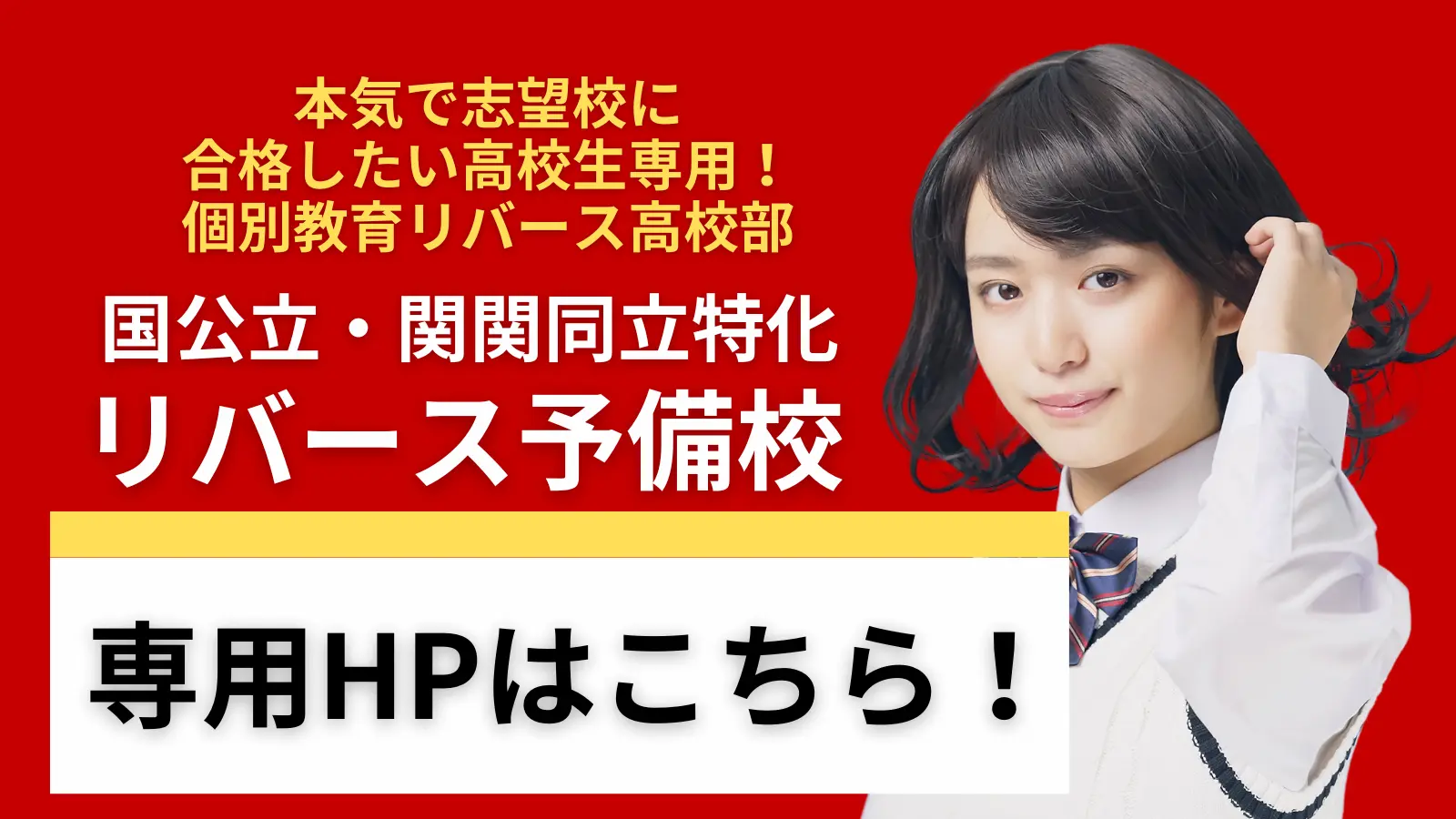
こんにちは。
個別教育リバースです。
学校休校期間中、開校時間を9:45~18:15にしていましたが、
学校再開に伴い、通常の時間帯14:00~22:00に戻させていただきます。
授業時間は、17:45~、19:10~、20:35~の時間帯です。
第2波、第3波に備えて、万全の感染対策で授業を行います。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
個別教育リバースです。
当校は、兵庫県の休業要請対象外(床面積100㎡未満)でしたが、感染防止の徹底に協力するため、4月14日(火)~5月6日(水)の期間を休校とさせていただきました。
しかしこれ以上の休校は、生徒さんの学力・学習習慣に大きな影響が出ると考えております。そこで、リバースでは新型コロナウィルス感染防止の措置を徹底の上、以下の日程・時間帯で業務を再開させていただきます。
5月7日(木)14:00~22:00 開校
5月8日(金)14:00~22:00開校
5月9日(土)14:00~18:00開校
5月10日(日)休校
5月11日(月) ~ (月)~(金)9:45~18:15の時間に開校時間を変更
(土)14:00~18:00開校
*10:00~10:50、11:00~11:50、12:00~12:50、の間は生徒の自習時間。
必ず週1回は自習に来ていただきます。(中3生は週2回)
授業時間は、14:00~15:15、15:25~16:40、16:50~18:05
学校再開までの間は、上記の時間帯に変更いたします。
学校が再開したときに、スムーズに学校生活に馴染めるように学習塾として最大限協力させていただきたい考えです。
ご理解ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
個別教育リバースです。
緊急事態宣言発令に伴う休業要請が兵庫県でも出される見込みとなりました。大阪府と足並みを揃えるとのことですので、床面積100平方メートル以上の学習塾も休業要請の対象となります。リバースは、上記の規定以下の学習塾ですが、感染拡大防止の徹底に協力するため、以下の期間を休校とさせていただきます。
4月14日(火)~5月6日(水)
上記の期間、授業はすべて中止となります。自習もできません。
ただし事務作業等により数日程度職員が14:00~18:00の間在室している場合があります。
リバース生には休校期間中の生徒別課題を用意し、理社テキストと一緒に配布いたします。配布日時は、4月15日(水)を予定しています。
休校期間の課題配布日以外の生徒の入室は禁止です。休校期間中は、教室長が週1~2回学習の進捗を確認するためご家庭に電話します。
以上になります。
こんにちは。
個別教育リバースです。
3月19日(木)に兵庫県公立高校入試結果が発表されました。
開校初年度で中3受験生は少ないですが、全員第一志望校に合格しました!
直接結果を伝えに来てもらい大変うれしかったです。
来年も全員第一志望校合格に向けて、様々な取り組み(一部集団授業の導入など)
を実施予定です。
ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
決して後悔はさせません。
こんにちは。
個別教育リバースです。
いよいよ明日から伊丹市・尼崎市の公立学校は休校となります。
昨日3/1(日)には兵庫県でも感染者が確認されました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200301/k10012308971000.html
西宮市在住の40代男性で、大阪市内の会社に勤務し、通勤にはJRを使っていたとのことです。マスク以外にも飲料水・食料品の買い占めなどが起きており、パニックに陥っている人もいます。1973年の石油危機と1927年の昭和金融恐慌を彷彿とさせる事態です。
しかしながら、こういう時にこそ冷静な行動をすることがみなさん、ひいては社会全体の利益になります。そこで今まで報道や専門家の話を総合し、本当に正しい情報・誤った情報を分けてみたいと思います。
① マスクは感染予防に効果があるか?
⇒ 3/1(日)にWHO(世界保健機関)がそれほど効果がないことを発表しました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200301-00000044-kyodonews-soci
⇒ 厚生労働省もHPで効果は限定的であると情報発信しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q18
もちろん、かかった人がそれ以上感染を広げないためには必要です。一方で、ウィルスは極小のため、花粉の侵入は防げても、マスクを通過するというのも事実です。また、目からも入るため、ゴーグルでもつけていないとウィルスを完全に防ぐことはできません。
② うがいは効果があるか?
⇒ 厚生労働省は、HPで以下のように述べています。
4. 小まめにうがい・手洗いをする
ウイルスのついた手で目や鼻、口などを触ると粘膜・結膜を通して感染することがあります。家族はこまめに石鹸を用いた手洗いもしくはアルコール消毒をしましょう。
ここで大切なのは、小まめにという言葉です。ウィルスはのどに付着して15分で体内に侵入すると言われています。15分おきにうがいしないと効果はないということです。
ではどのようにすればいいのでしょうか?
前に「最強のインフルエンザ対策について」という記事を書きました。
https://kobetsu-reverse.jp/news/20191203/605
お医者さんも実践している、カテキン入りのお茶をちびちび(15分おきに)飲むのが効果的のようです。
③ 手洗いは効果があるか?
⇒ これが最も効果の高い感染予防法です。上記の厚生労働省HPにもそのように記されています。
これには理由があります。生徒さんを見ていてもよく手で自分の顔を触っています。これは大人でも同様で、無意識に行っている行動です。汚れた手で、顔(目・鼻・口)を触れば、当然感染のリスクは上がります。中には、マスクで完全防備していながら、目をこすっている人もたまに見かけます。まさに本末転倒です。
以上、なるべく根拠をもって書かせていただきました。新聞で専門家の発言を読んだり、TVを見て確度の高いと思われるものを中心にまとめました。
こんにちは。
個別教育リバースです。
さて、ご存じの通り2月27日(木)、政府は新型コロナウィルスの感染拡大を受け、全国すべての小・中・高校などを週明け3月2日(月)から臨時休校を要請する方針を発表いたしました。伊丹市・尼崎市は3月3日(火)~ 25日(水)の期間、臨時休校することとなりました。
休校なので、部活動もありません。基本、家にいなさい、ということです。人の多く集まる場所へ行ったり、不要不急の外出は控えるようにしていただきたいと思います。
一方で、学校がないということはお子さんの勉強する機会が奪われることでもあります。
リバースでは、兵庫県と生徒さんの通っている学校からコロナウィルス感染者が出ていない状況ですので、通常通り開校とさせていただきます。
万が一、通塾生徒さんの学校からコロナウィルス感染者が出た場合は休校の対応を検討いたします。その際は、ご連絡させていただきます。
*新たな情報が出て、塾として休校せざるを得ない場合も同様です。
*スタッフは全員マスクを着用し、授業を実施します。定期的に換気を行い、常に空気清浄加湿器を運転させています。ウィルス除菌用のウェットティッシュで手を拭いてもらいます。汚れた手で顔を触らないように指導を徹底しています。
以上、ご不便をかけるかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
個別教育リバース
こんにちは。
個別教育リバースです。
英語民間試験活用に続き、大学入試改革の柱であった国語・数学記述式が見送りとなりました。国語の記述式批判が大半であり、数学の記述式についてはあまり報道されていません。私は、英語民間試験活用(特に、スピーキング導入)には大反対でしたが、国語・数学の記述式問題導入には賛成でした。理由としては、マークシート式入試問題を外注している、あるいはセンター試験で代用している私立大学受験生でも、強制的に記述試験対策をしないといけないからです。日本には770以上の大学があり、その8割が私立大学です。その多くでマークシート方式が採用されています。マスコミの報道で、記述式は2次試験で行うのから実施しなくてもいいのではないか、という意見が散見されました。しかし、それは大学全体の1~2割の国公立大学のみに焦点を絞った話だったのです。一部難関私立大学を除くほとんどの私立大学では、マークシート方式が採用されているため、記述力を測れるようにはなっていません。また、マークシート方式では、受験生の本当の学力を測ることは出来ません。マークシート方式の弊害については、数学者の芳沢光雄氏も著書(『論理的に考え、書く力』光文社新書、2013年、第2章)で指摘しています。
採点体制の不備など技術的な問題点が噴出しました。私もまさかここまでいい加減な採点方法・体制とは思ってもみませんでした。
しかし、本気になって受験生の思考力を問う入試にすることには意味があると思います。また、以前指摘したように、英語ライティング試験導入も必要と思います。民間試験でスピーキング試験を導入しなくても、ライティングだけで完璧に英語力が測れるからです。もちろん、ライティング試験の採点にネイティブチェックを入れるべきかどうかの問題も発生します。いろいろお金も絡む問題ですが、未来への投資として、国にはしっかりとした採点体制で記述式導入に取り組んでいただきたいと願います。
こんにちは。
個別教育リバースです。
孫子の兵法には、次の有名な言葉があります。
「彼を知り己を知れば、百戦してあやうからず」(敵の実情を知り、また自軍の実態を知る。そうすれば、百たび戦っても危ういことはない。)(湯浅 邦弘『孫子・三十六計』角川ソフィア文庫、2008年、P61)
ここでは、敵=志望大学 自軍の実態=自分の学力、と考えてみましょう。
志望大学を知るためには、過去問研究が欠かせません。
自分の学力を知るには、模擬試験結果の詳細な分析が欠かせません。
模試は単にやり直すだけではなく、成績表を精査することで自分の弱点を知る強力な武器になります。受験生の方は、判定に一喜一憂するのではなく、ぜひ成績表をよく読み込んでください。自分には何が欠けており、何をしなければいけないかが分かります。
また、生徒からいつ過去問題集(赤本)をやればいいですか?という質問をよくされます。
これには、2つの考え方があります。1つは、4月くらいの段階で一度解いてみる。そして、ショックを受けて、入試までにしないといけないことを逆算して計画する。
もう1つは、ひたすら基礎基本の習得を重視し、過去問演習は12月に入ってから行う。
私の考えは後者です。ある程度基礎学力を身に付けてから解く方が効果的だと考えています。
あらゆる受験指導のプロ中のプロと言われる小林 公夫氏は、試験委員が変わった時に起こる「問題の周期を知ること」が過去問研究において重要と述べています。続けて、過去問研究の具体的やり方として以下のように述べています。
「一0年分の過去問を用意する、目指す大学の教授の研究対象を調べる、インターネットや図書館など、情報を入手する方法はいろいろあります。目指す大学に学部の先輩がいれば、教養課程で使用している教科書を拝借し、分析させてもらうのも一つの方法です。
入手した情報を駆使し、過去の情報と照らし合わせて分析すること、そこから次の展開を推測すること。この科学的・効率的方法をぜひとも実践し、難関を勝ち抜いていってください。」(小林 公夫『東大生・医者・弁護士になれる人の思考法』ちくまプリマ―新書、2010年、P123)
小林氏によれば、特に「目指す大学の教授の研究対象を調べる」のが効果的なのは、数学と理科(物理・化学・生物)とのことです。
私は、古文と社会(日本史・世界史・政経)も効果的だと思います。大学のHPなどで教員の専攻・研究分野を探す際、過去問と照らし合わせやすいからです。ぜひ受験生のみなさんは実践してみてください。
こんにちは。
個別教育リバースです。
12月になりましたので、本日はインフルエンザ対策について書きます。前に見たTV番組で、お医者さんが実践しているインフルエンザ対策について特集していました。以下がその内容です。
http://www.news24.jp/articles/2018/02/08/07385171.html
他の番組などの情報も踏まえて、リバースでは以下の対策を徹底しています。
①授業をする講師は全員マスク着用(咳が出ている生徒にはマスク着用をお願いしています。)
②空気清浄加湿器の稼働(湿度が50%以下にならないように注意しています。)
⇒インフルエンザウィルスは湿度40%以下で活発に空気中を浮遊するそうです。
③塾に来た時、ウィルス除去のウェットティッシュで全員に手・指を拭いてもらっています。(特に、指先と爪を念入りに拭くように指導。爪にウィルスが付着している可能性が高いそうです。)⇒ 全員に手を洗わせることができないための措置です。
④全員にインフルエンザの予防接種を推奨(特に、受験生には強く勧めています。)
⇒ 仮にインフルエンザにかかっても軽く済むとのことです。
⑤手で顔を触るクセのある生徒にはしつこいくらい触らないように注意しています。
⇒ 目をこするなどもってのほかです!!風邪・インフルエンザにかかる可能性がかなり高くなります!!
⑥授業中であっても、講師・生徒ともに飲み物を飲むことを推奨しています。
⇒ ジュースを除きます。記事にもある通り、カテキンを含むお茶をちびちび飲むのがインフルエンザウィルスの死滅には有効とのことです。
上記①~⑥の中で、家でも教室でも簡単にできる予防として私が心がけているのが、
1)手を清潔にする。(頻繁に洗う。)
2)手で顔を触らない。(触る場合は、ハンカチを使う。)
3)お茶をちびちび飲む。(うがいをする時点ですでにウィルスがのどに付着しているそうです。お茶で胃に流し込んで胃酸で死滅させる方が効果的とのことです。)
ぜひみなさんも参考になさってください。インフルエンザにかからないことを祈っております。
こんにちは。
個別教育リバースです。
子どもであればスポーツが上手になりたい、勉強ができるようになりたい。
大人であれば、資格試験に合格したい、仕事ができるようになりたい。
これらは、子ども・大人を問わずみんなが望むことではないでしょうか。しかし、大半の方々が経験済みだと思いますが、なかなか思い通りにはいきません。
3日坊主でやめてしまったり、中途半端にやってほとんど何も身につかないなどです。
これには3つの原因が考えられます。
①最初からあまりやる気が出ずにすぐにやめてしまう。
②最初から飛ばし過ぎて、自分の能力以上のことをやった結果、嫌になりやめてしまう。
③無理のない範囲でしか努力しないため、成長が感じられずやめてしまう。
①は周りに流されたか、ブームにのったかなので真剣さが足りません。
②は、計画立てて物事を実行せず、自分の能力を過大評価した結果です。
③は、自分のことを適正に評価していることと続けている点で①②よりは地に足がついて
おり、あともう一歩と言ったところです。
それでは、どうすればいいのでしょうか?
シンクタンク代表で多摩大学大学院名誉教授の田坂広志氏は以下のように述べています。
「・・・人間の能力というものは、「一00」の能力を持った人間が、「九0」の能力で仕事に取り組んでいると、その仕事を、たとえ「一000時間」行ったとしても、確実に力はおとろえていく。
もし、「一00」の能力を持った人間が、自身の能力を高めていきたいと思うならば、「一一0」や「一二0」の能力が求められる仕事に集中して取り組む時間を、たとえ「毎週数時間」でよいから持たなければならない。逆に、その「毎週数時間」を持ち続けるならば、確実に能力は高まっていく。」(田坂 広志『知性を磨く』光文社新書、2014年、P48)
田坂氏は、自分の能力より少し負荷のかかることをやり続ければ能力は高まると述べています。この考え方は、勉強にも適用できます。
基礎学力がない状態で、難しい応用問題を解こうとしても全く歯が立たず、嫌になってしまいます。逆に、すでに出来る簡単な問題ばかり解いていると、退屈になってきます。
どちらも学習を継続させることは困難です。今の自分の学力より少し上の問題をきちんと考え、解いていけば、学習能力は確実に高まります。
上記はどんなことにも応用できる考え方なので是非、スポーツ等でも実践してください。
© 個別教育リバース. All Rights Reserved.